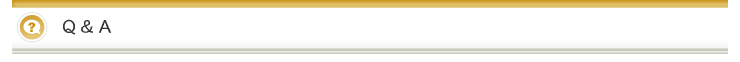
■福祉用具専門相談員についてのQ&A
■福祉用具専門相談員指定講習についてのQ&A
■福祉用具専門相談員のスキルアップについてのQ&A■福祉住環境コーディネーターについてのQ&A■全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)についてのQ&A |
|||||||||
福祉用具専門相談員とは介護保険制度は、要介護状態となった高齢者等に対して、自立支援の理念のもと、ケアプランに基づき、多様なサービスを組み合わせて提供しながら、高齢者等の日常生活を支えるための仕組みです。 福祉用具サービスは、介護保険サービスの1つです。高齢者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて利用目標を定めるとともに、適切な福祉用具を選定し、利用者がその目標に向けて福祉用具を活用した生活を送れるよう、専門職である福祉用具専門相談員が支援するものです。 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況や生活環境に適した福祉用具について提案を行うことにより、利用者が適切な福祉用具を選定することを支援する役割を担っています。 |
|||||||||
福祉用具専門相談員についてのQ&A
|
|||||||||
福祉用具専門相談員はどのような資格ですか?
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職です。他の介護保険サービスの専門職と連携しながら、高齢者の自立した生活を、福祉用具でサポートします。
▲ページトップへ戻る
(主な業務)
|
|||||||||
 |
|||||||||
福祉用具専門相談員の資格はどのように取得するのですか?
都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。講習の最後に、習熟度を測るための修了評価(筆記の方法による)がおこなわれます。
▲ページトップへ戻る
|
|||||||||
 |
|||||||||
福祉用具貸与事業所でご利用者の相談に応じるには、福祉用具専門相談員指定講習を修了する必要がありますか?
福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
福祉用具専門相談員指定講習についてのQ&A
|
|||||||||
指定講習ではどのようなことを学ぶのでしょうか?
福祉用具専門相談員の役割や、介護保険制度等に関する基礎知識、高齢者と介護・医療に関する知識、個別の福祉用具に関する知識・技術(演習含む)、福祉用具サービス計画(個別援助計画)等について学習します。 カリキュラムの詳細はこちら ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
指定講習はどこで受けられるのでしょうか?
都道府県で指定を受けた研修機関(指定講習事業者)が全国各地で開催しています。お近くの研修機関を知りたい場合は、各都道府県のホームページをご覧ください。なお、研修機関から掲載依頼があったものにかぎり、「研修会・イベント」ページに開講情報をご紹介しています。あわせてご参照ください。 ※都道府県によっては、開講情報や研修機関の一覧を掲載していないところがあります。 その際は、インターネットで研修機関を検索していただくか、県庁へ電話でお問い合わせください。
|
|||||||||
 |
|||||||||
福祉用具専門相談員指定講習の受講資格を教えてください。
受講資格の制限は特になく、どなたでも受講することができます。ただし、研修機関によっては、指定講習に定められる到達目標に達することが困難な方の受講をお断りするケースがあるようです。くわしくは研修機関にお問い合わせください。▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
指定講習の修了証を紛失してしまったのですが、再発行はできますか?
受講した研修機関で再発行を依頼することができます。研修機関に直接お問い合わせください。▲ページトップへ戻る |
|||||||||
福祉用具専門相談員のスキルアップについてのQ&A
|
|||||||||
福祉用具に関連する他の資格はありますか?
以下のような主な研修・検定を受けて所定の成果を修めると、実施機関が認定する資格を取得することができます。福祉用具専門相談員として従事されている方がレベルアップのために多く受けています。 ●福祉用具プランナー他 公益財団法人テクノエイド協会 ホームページ:http://www.techno-aids.or.jp/ Tel:03-3266-6880 ●福祉用具選定士 一般社団法人日本福祉用具供給協会 ホームページ:http://www.fukushiyogu.or.jp/ Tel:03-6721-5222 ●福祉住環境コーディネーター検定試験 東京商工会議所 ホームページ:https://kentei.tokyo-cci.or.jp/fukushi/ Tel:03-3989-0777 詳しくはこちらをご覧ください。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
福祉住環境コーディネーターとは福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。 医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示します。また福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスします。 バリアフリーとは、段差をなくしてスロープを付けることだけではありません。年のとり方が人それぞれであるように、必要とされるニーズも千差万別です。そのため、クライアントの特性にマッチした住環境を提案・実現するには、様々な分野の専門家とわたり合い調整を行うことのできる総合的な知識が欠かせません。 わが国は世界でも類を見ない速さで超高齢社会に突入しており、あらゆる業界において高齢者を意識したビジネスに大きくシフトしつつあります。このような状況の中、医療・福祉・建築について総合的な知識を身に付けている福祉住環境コーディネーターへの社会的ニーズは確実に高まっています。 |
|||||||||
福祉住環境コーディネーター(FJC)についてのQ&A
|
|||||||||
 |
|||||||||
福祉住環境コーディネーター(FJC)とはどのような資格ですか?
福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。 医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示します。また福祉用具や諸施策情報などについてもアドバイスします。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
福祉住環境コーディネーター(FJC)の資格はどのように取得するのですか?
東京商工会議所が実施する試験を受験する必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定試験 https://kentei.tokyo-cci.or.jp/fukushi/ ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)についてのQ&A
|
|||||||||
 |
|||||||||
協会はどのような活動をおこなうのですか?
会員の皆様のご協力を得て以下のような活動を行い、福祉用具専門相談員のステータスを高めていきたいと考えています。 (1)福祉用具貸与・販売サービスの専門職としての職業倫理の確立 (2)福祉用具専門相談員への研修事業 (3)会員向けホームページの運営 (4)会員向けメールマガジンの配信 (5)厚生労働省、地方自治体、保険者等への提言、及び連携 (6)関係者との連携強化 (7)福祉用具貸与・販売サービスの普及・啓発事業▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
会員になるためにはどうすればよいのでしょうか?
所定の申込用紙に必要事項をご記入いただき、資格証の写しを添付のうえ、1.申し込みフォームへの入力、2.FAX・郵送・E-mail(資料添付)のいずれかの方法で、事務局にお送りください。詳細はこちら。なお、会員としての正式登録までの手続きは、以下のように進めてまいります。 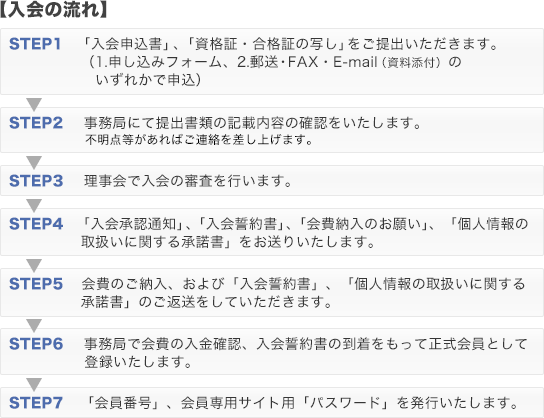 ▲ページトップへ戻る
▲ページトップへ戻る
|
|||||||||
 |
|||||||||
入会金は必要なのでしょうか。また、会費の支払い方法について教えてください。
入会金は特に必要ありません。会費はA会員、B会員とも1万円(年額)です。お申し込みを承った後、所定の手続きを経て、事務局から別途請求書をお送り致します。
▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
A会員とB会員の違いを教えてください。
以下のとおりです。入会後にA会員、B会員の違いによって会員サービスが異なるわけではありません。あくまで資格管理の都合で会員種別を分けています。 A会員…福祉用具専門相談員指定講習の修了者であって、本会の目的に賛同する方 B会員…専門的有資格者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)であって、本会の目的に賛同する方 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
会員サービスについて教えてください。
会員証の発行/会員専用サイトの閲覧/会員価格でのお得な商品購入/会員限定研修への参加/「ふくせんレポート」等の送付/「お知らせメール」の配信/など、様々なサービスを提供しております。 詳細はこちらをご覧ください。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
賛助会員制度について教えてください。
本会には、定款第6条に基づく「賛助会員制度」があります。賛助会員は、本会の趣旨に賛同いただき、本会の事業を賛助していただける個人または団体です。 【賛助会費】 法人:一口 10万円(一口以上、年額) / 個人:一口 1万円(一口以上、年額) 【申込方法】 こちらをご覧ください。 【特 典】 ●賛助会員には、正会員(A、B会員)と同様の会員サービスを提供いたします。 ただし、一部の権利、要件(定時総会における議決権、ブロック長への就任要件)は満たしませんのでご了承ください。 ● 法人賛助会員は、ホームページや印刷物で、賛助会員である旨をご案内させていただきます。 ● そのほか、本会が主催する福祉用具専門相談員を対象とした催し等に参加・協力を依頼することがあります。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
会員としての義務などは何かありますか。
特にありませんが、本会の定款、または規則等に違反したときや、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたときなどは、除名することがあります。▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
会員IDとパスワードの再発行について教えてください。
会員IDは会員番号:0もしくはFで始まる5桁の番号となります。 またパスワードは会員証送付時の書類に記載しております。 会員IDまたはパスワードをお忘れの方は、お手数をお掛けしますが、本会代表アドレス(info@zfssk.com)宛にメールの件名を「会員ID・パスワード再発行依頼」としていただき、本文にお名前・勤務先等を記入して、お問い合わせをお願いいたします。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
退会の手続きについて教えてください。
退会届に記入して1.郵送・FAX・E-mail(資料添付)、2.退会申込みフォームのいずれかにてご連絡ください。 ■郵送でお手続きされる場合 【送付書類】 退会届 (PDF/ワード) 【送付先】 〒108-0073東京都港区三田2-14-7ローレル三田404 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 事務局
■退会申込みフォームより送信される場合 メニューの「会員ログイン」よりログインしていただき、「諸手続き」のページにてご確認ください。 ▲ページトップへ戻る |
|||||||||
 |
|||||||||
| その他、ご不明な点がございましたら、お気軽に協会事務局までお問い合わせください。 ◆一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 事務局
|
|||||||||