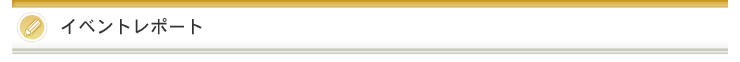契約をする際の判断材料という観点でみると“情報の公表”がいかに大きな意味をもつのかがわかる。木間先生いわく、
「介護サービスの情報公表は、事業者が好意で行うわけでも、サービスで行うわけでもありません。事業者に課せられている義務なのです。事業者の方々には、そのことをはっきり申し上げたいと思います。」
公表されている情報は、おおまかに次の通り。
●誰が…基本情報 実績等
●いつ…基本情報 営業時間等
●いくらで…基本情報 介護給付サービス費用、介護給付以外のサービス費用等
●どのような…基本情報 スタッフ情報(人数、経験など)等
●どのように…調査情報 相談、アフターフォローの体制等
●利用者の意見を把握する取り組みの有無、開示しているかどうか
●第三者機関による評価の有無、開示しているかどうか
このうちの調査情報(調査員が訪問して確認する情報)では、次の4項目が重要である。
○用具の選定前に利用者(消費者)と面談しているか
○相談・苦情対応の結果を利用者に説明しているか
○搬入日から10日以内に、使用状況を確認しているか
○6か月に1回以上訪問し、使用状況を把握しているか
この4項目すべてをクリアしている事業者であれば、福祉用具をレンタル(あるいは購入)した後で、身体に合わないとか、操作方法がわからない、などといった不安や不満を抱えることはないはずである。
相談員の人数などの基本情報と合わせれば、自分が契約したい事業所かどうか、読み取ることができる。契約する際は、自分が必要な対応を十分にしてくれる事業所を選べばいいのである。しかし、ここには大きな問題がある。現在公表されている情報は、「介護サービスについての知識をもたない高齢者にわかれというにはあまりに酷な情報」(木間先生)なのだ。