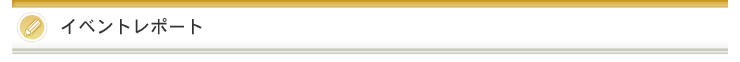安田勝紀(やすだ・かつのり)氏プロフィール
安田勝紀(やすだ・かつのり)氏プロフィール
株式会社シルバー産業新聞社編集長。1949年、奈良県生まれ。75年立命館法学部卒業、同年ドラッグマガジン入社。95年11月「シルバー産業新聞」を創刊。99年9月シルバー産業新聞社設立、同紙編集発行人として現在に至る。公職としては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「福祉用具実用化推進事業」評価委員。テクノエイド協会「福祉用具臨床的評価事業」苦情処理・サーベイランス部会委員。福祉用具国民会議運営メンバー。
「介護保険制度がスタートして今日まで10年の間に、地域の中での事業者の確保や、福祉用具サービスの育成など基盤整備が図られ、日本全国どこへ行っても一定の基準を満たすサービスが受けられるようになった。とりわけ福祉用具に関しては、要介護高齢者400万人に対し、よくフォローできている」と語るのは、シルバー産業新聞編集長として介護業界の動向を見守ってきた安田勝紀氏だ。
しかし周知のとおり、今後の介護サービス必要量は増加していくが、昨年、東京都は施設拡充の緊急整備に着手した。約100万人いる75歳以上の高齢者が20年後には倍増し、年齢が高くなれば要介護度が高くなることから、今以上の介護サービスが必要になることが予想される。それに対し、“サービス提供者”の側はどうか。わが国における労働力人口が減少を続けている以上、マンパワーをつぎ込むという策だけでは必ず限界がくる。そこにある課題は、今後の介護サービスをどう組み立てていくべきかだ。
「要介護度が進んでいくと、各家庭での対応は難しくなります。要介護4では5割、要介護5では3人に2人が施設等(グループホームを含む)に入っています。これは現在の地域包括ケアでの対応の難しさを表しています。要介護度が高くなっても、独居や老老介護であっても、適切に福祉用具や住宅改修を活用して少しでも長い期間、在宅で暮らし続けられるようにすることが、福祉用具事業者として、もっとも考えなければならないテーマではないでしょうか」(同氏)。
ところが、今後の介護政策に影響を与える「地域包括ケア研究会報告書」では、福祉用具についてほとんど触れられておらず、ケアマネジメントの中に福祉用具をどのように組み込むかというテーマも出てこない、と安田氏は嘆く。