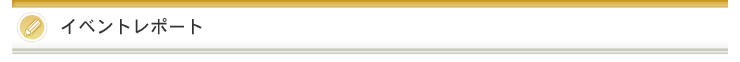▲東畠 弘子氏
福祉用具個別援助計画書の開発からその後の普及・調査活動のキーマンである東畠弘子氏は、今回発表された「改訂版福祉用具個別援助計画書」および「改訂版モニタリングシート(訪問確認書)」の説明、紹介を行った。具体的な改訂内容の解説とともに両様式を作成することの意義、狙いを改めて話した。
「福祉用具の提供における個別援助計画書作成のメリットとして『可視化』することで見えてくるもの、があげられます。①記録することで第三者にも理解しやすく、担当者が交代してもサービスの継続がスムーズに、②選定理由が明確になるので、ご利用者の状態が変わった時に機種変更を提案しやすい(理解の助けにもなる)、③留意点を記載することが、取り扱いや事故防止に役立つ、④目標を立てることで達成度が検証できる、などです」(同氏)。
個別援助計画書作成時のアセスメントを通じ、利用者がどんな福祉用具を欲しているのか、何を期待しているのかがわかる。そして、モニタリングによってその経過、結果が明らかになる。これまでは個々の相談員のスキルによる格差が目立った“把握力” “提案力”。その底上げ・標準化をこの2枚のシートが可能にする。
さらに、改訂に際して行ったアンケート結果をみるとこの様式を作成・使用することが、ケアマネジャーとの連携強化やケアプランの理解、個々の意識改革やスキルアップにつながった例が多数認められているという。