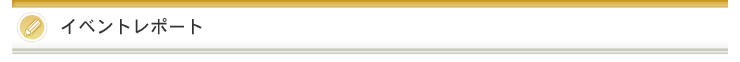阿部 勉氏
(あべ・つとむ)
健康科学博士、理学療法士。植草学園大学保健医療学部専任講師
阿部氏が語る、事故を防ぐ3つのポイントとは何か?
①アセスメント(適切な評価。その方の心身の状態に対し、どういった福祉用具が必要なのか)、②メンテナンス(効率よく使い続けるため、長期的に関わっていかなければならないこと)、③モニタリング(劣化、変化していく用具への対処)である。これらは物的なことだけではなく、ハード・ソフト両方において支援していかなければならないものであり、三位一体で行って初めて、効率のよい事故防止が実現する。
阿部氏はセラピストとして訪問しているご利用者宅で、まず“スピーディーな導入”に驚いたという。歩行器を導入した頸椎損傷の患者さんなのだが、その介護プランにおいては、通院先のセラピストと相談したあとすぐにケアマネジャーが動き、福祉用具専門相談員がきて導入されるにいたった。
「私は週に1回うかがうのですが、前の週は何もなかったのに、次の週うかがったらすでに歩行器が導入されており、利用者さんは『生活が一変したよ』 と。20 年間、理学療法士をしていますが、そんな言葉を聞いたのは初めてでした。福祉用具のちからはすごい」(同氏)。
阿部氏のような“セラピスト”が在宅に訪問するケースはまだ少ない。セラピストという立場ではあるが、週または月に1回訪問するという状況下では、福祉用具についてのモニタリングはもちろんメンテナンスもできない。
「利用者さんの生活に最も近いところにいる介護職の方がモニタリングをし、福祉用具専門相談員の方がメンテナンスとアセスメントをするというのがやはり良いかたちだと思います。事故防止の点からも。アセスメントについては、われわれセラピストも連携することができるでしょう」(同氏)。